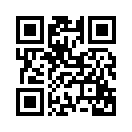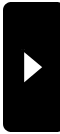2010年12月19日
テーマ『日中外交・対中ODA』 (2010/12/17)
こんにちは、国際総合学類1年の中川雄貴です。
初のブログ投稿で緊張しております。
2010年12月17日のIIRAは「日中外交」をテーマにやりました。
一年生だけでしたけど、新メンバーも加わり楽しく熱いIIRAだったと思います。
具体的には、
前半では『日中共同声明』、『日中平和友好条約』の締結の過程に
何か問題はなかったのだろうか?、ということについて話し合い、
後半にはその問題のうちの一つの対中ODAについて議論しました。
まずは前半について・・・・・
実際には、今現在日中間(また第三国を含めて)でもめている諸問題の発端がこれら2つの日中間の条約にあったりします。
①日中共同声明(1972年9月29日)
日本と中華人民共和国の国交正常化の文書です。
これに関する問題が
・台湾問題・・・・・大陸の中華人民共和国との国交を結ぶことは、台湾の中華民国との関係を切ることを意味し、日華平和条約は失効。
・対中ODA問題・・・・・中国が日本に対して損害賠償の請求を放棄したことに日本側は感激する一方で、後ろめたい気持ちもあり、それが多額のODAという形で表れている。しかし、中国はそれを「損害賠償の代わり」と受け止めて感謝しない、ということが続いてきた。
②日中平和友好条約(1978年8月12日)
これに関する問題が
・尖閣諸島領有権問題・・・・・1960年代に尖閣諸島付近で豊富な石油資源が埋蔵されていることが明らかになって以来、中国と台湾が尖閣諸島の領有権を主張。これに関して、日中平和友好条約を結ぶことに慎重な自民党議員たちが「友好条約を締結するなら、尖閣諸島の日本の領有権を中国に認めさせるべきだ」と主張。この主張に対して、1978年4月12日、中国漁船200隻が尖閣諸島周辺に集結し、また日本の領海を侵犯。領有権は棚上げにされ、条約締結。
後半戦へ・・・・・
あなたは対中ODA継続について賛成ですか?反対ですか?
継続の主張、継続反対の主張いろいろあります。
・継続の主張
① 円借款は賠償の代替ではないが、賠償を放棄した中国の温情も忘れないでほしい。
② ODAは互恵的、相互的なものである。ODAは中国に進出する日本企業も助けている。
③ ODAの必要性は減っているものの、内陸部と農村部にはまだまだ必要な地域が残っている。
④ 中国は、日本から受けた借款をきちんと返済しており、しかも円建てなので元利が確実に戻ってくるいわば優良債権だ。
⑤ 対中円借款の7割は、環境分野で行われている。隣国の環境破壊を防ぐことは、日本の国益にもかなう。
・継続反対の主張
① 日本は巨額の財政赤字を抱え、もはや財政的余裕はない。
② 中国は、軍事力を増強しているが、これはODA大綱の「軍事支出等の動向に十分に注意を払う」との原則に抵触するおそれがある。
③ 我が国のODAに対し、中国側からは謝意がない。中国はまた、日本要人の靖国神社参拝に対して文句を言うなど、友好的でない。
④ 中国の経済発展は著しく、もはや援助を必要としていない。
⑤ 中国は被援助国でありながら、北朝鮮をはじめとして、外交戦略上重要な国々に対しては、軍事援助を含め、かなりの額の経済援助を行っている。
今回戦後の日中間の条約を調べてみて、
これら2つの条約は日中両国にとってすごく意義のある条約ですが
『臭いもの(歴史問題、領土問題)に蓋をする』感が否めないような・・・
対中ODAについての議論は参加者みんな知識が豊富で盛り上がりました。
対中だけでなく日本にとってのODAの意義等にも触れることができ充実でした。
参考
池上彰『そうだったのか!中国』(集英社/2007)
外務省 対中国に関する基礎資料 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kondankai/senryaku/21_shiryo/pdfs/shiryo_2_1.pdf
次回は2011年1月7日です。
発表者は未定ですが・・・・
楽しみにしていてください
それではみなさん
 Merry Christmas&Happy New Year
Merry Christmas&Happy New Year
初のブログ投稿で緊張しております。
2010年12月17日のIIRAは「日中外交」をテーマにやりました。
一年生だけでしたけど、新メンバーも加わり楽しく熱いIIRAだったと思います。
具体的には、
前半では『日中共同声明』、『日中平和友好条約』の締結の過程に
何か問題はなかったのだろうか?、ということについて話し合い、
後半にはその問題のうちの一つの対中ODAについて議論しました。
まずは前半について・・・・・
実際には、今現在日中間(また第三国を含めて)でもめている諸問題の発端がこれら2つの日中間の条約にあったりします。
①日中共同声明(1972年9月29日)
日本と中華人民共和国の国交正常化の文書です。
これに関する問題が
・台湾問題・・・・・大陸の中華人民共和国との国交を結ぶことは、台湾の中華民国との関係を切ることを意味し、日華平和条約は失効。
・対中ODA問題・・・・・中国が日本に対して損害賠償の請求を放棄したことに日本側は感激する一方で、後ろめたい気持ちもあり、それが多額のODAという形で表れている。しかし、中国はそれを「損害賠償の代わり」と受け止めて感謝しない、ということが続いてきた。
②日中平和友好条約(1978年8月12日)
これに関する問題が
・尖閣諸島領有権問題・・・・・1960年代に尖閣諸島付近で豊富な石油資源が埋蔵されていることが明らかになって以来、中国と台湾が尖閣諸島の領有権を主張。これに関して、日中平和友好条約を結ぶことに慎重な自民党議員たちが「友好条約を締結するなら、尖閣諸島の日本の領有権を中国に認めさせるべきだ」と主張。この主張に対して、1978年4月12日、中国漁船200隻が尖閣諸島周辺に集結し、また日本の領海を侵犯。領有権は棚上げにされ、条約締結。
後半戦へ・・・・・
あなたは対中ODA継続について賛成ですか?反対ですか?
継続の主張、継続反対の主張いろいろあります。
・継続の主張
① 円借款は賠償の代替ではないが、賠償を放棄した中国の温情も忘れないでほしい。
② ODAは互恵的、相互的なものである。ODAは中国に進出する日本企業も助けている。
③ ODAの必要性は減っているものの、内陸部と農村部にはまだまだ必要な地域が残っている。
④ 中国は、日本から受けた借款をきちんと返済しており、しかも円建てなので元利が確実に戻ってくるいわば優良債権だ。
⑤ 対中円借款の7割は、環境分野で行われている。隣国の環境破壊を防ぐことは、日本の国益にもかなう。
・継続反対の主張
① 日本は巨額の財政赤字を抱え、もはや財政的余裕はない。
② 中国は、軍事力を増強しているが、これはODA大綱の「軍事支出等の動向に十分に注意を払う」との原則に抵触するおそれがある。
③ 我が国のODAに対し、中国側からは謝意がない。中国はまた、日本要人の靖国神社参拝に対して文句を言うなど、友好的でない。
④ 中国の経済発展は著しく、もはや援助を必要としていない。
⑤ 中国は被援助国でありながら、北朝鮮をはじめとして、外交戦略上重要な国々に対しては、軍事援助を含め、かなりの額の経済援助を行っている。
今回戦後の日中間の条約を調べてみて、
これら2つの条約は日中両国にとってすごく意義のある条約ですが
『臭いもの(歴史問題、領土問題)に蓋をする』感が否めないような・・・
対中ODAについての議論は参加者みんな知識が豊富で盛り上がりました。
対中だけでなく日本にとってのODAの意義等にも触れることができ充実でした。
参考
池上彰『そうだったのか!中国』(集英社/2007)
外務省 対中国に関する基礎資料 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kondankai/senryaku/21_shiryo/pdfs/shiryo_2_1.pdf
次回は2011年1月7日です。
発表者は未定ですが・・・・
楽しみにしていてください

それではみなさん
 Merry Christmas&Happy New Year
Merry Christmas&Happy New Year
2010年09月19日
イスラム教は悪なのか
9月17日のイイラの活動を報告します。ハラトモです。初投稿です。

トルコにラマダーンの時に行ってきました。
トルコの魅力、イスラム教の本当の姿、旅で感じたことがかなりあったんで、そのことが少しでも伝わればうれしいです。
旅報告&政教分離&イスラム教のイメージについて、意見交換しました。
一般的には、
イスラム教=悪 だというイメージがあります。
でも、実際イスラム教の思想って、本当に悪に繋がるのでしょうか。
そもそも、日本人の宗教観ってどのようになっているんでしょうか。
宗教って何なのか。
みたいなことを話し合いたかったのですが、
先輩方が本当にいろいろなことを知っていて、自分がトルコを旅してもやもやしてたことがすっきりしてきました。
「国」としての価値観が、個人の宗教も民主主義も規定してきているのかもしれないな、と思い始めました。
これからもできるだけ顔をだすんで、よろしくお願いします!
トルコにラマダーンの時に行ってきました。
トルコの魅力、イスラム教の本当の姿、旅で感じたことがかなりあったんで、そのことが少しでも伝わればうれしいです。
旅報告&政教分離&イスラム教のイメージについて、意見交換しました。
一般的には、
イスラム教=悪 だというイメージがあります。
でも、実際イスラム教の思想って、本当に悪に繋がるのでしょうか。
そもそも、日本人の宗教観ってどのようになっているんでしょうか。
宗教って何なのか。
みたいなことを話し合いたかったのですが、
先輩方が本当にいろいろなことを知っていて、自分がトルコを旅してもやもやしてたことがすっきりしてきました。
「国」としての価値観が、個人の宗教も民主主義も規定してきているのかもしれないな、と思い始めました。
これからもできるだけ顔をだすんで、よろしくお願いします!
2010年05月20日
ロシア留学よもやま話【2010.05.14定例活動】
ロシア語をはじめたきっかけは、
マイナーだからということで、
でもロシア語が好きになり、約1年間留学していた
メンバーの発表でした。
ロシア語とってる1年生など、
全体で11名の参加で、盛り上がりました

飛行機から見たロシア
さて、話は想像以上に準備されたレジメと共に約2時間半ほぼ休みなく展開しまして
その状況の一部を紹介するのみなりますが、
簡単にフィードバック!!
(後日、発表者が修正してくれるかも??)
ロシアのイメージのブレーンストーミング
でかい、寒い。
天然資源。
シベリア鉄道。
車が動かない。
結局、やっぱまとめられないので、
びっくりしたところをまとめました。
驚きロシア
・ロシア通貨ルーブル→日本円は、日本では交換できない!
(日本円→ロシアルーブルは、成田などで交換できるけど。。。)
・冬の日照時間は5時間。
(朝暗い時期に家を出て、学校帰るときも暗い)
・国際空港でも英語が通じない。
(町の中でも英語×、義務教育で英語は習うらしいが話せる人はほとんどいない)
・ベラルーシ、ロシア、リトアニアは自殺率が高い。
(10万人当たり30人以上、日本は25人ぐらい)
↑その原因の1つ。。
・アルコール中毒が多い。
(ウォッカが今年から値上げ)
・ロシア人は中国人が嫌い。
(日本人には優しい)
マイナーだからということで、
でもロシア語が好きになり、約1年間留学していた
メンバーの発表でした。
ロシア語とってる1年生など、
全体で11名の参加で、盛り上がりました


飛行機から見たロシア
さて、話は想像以上に準備されたレジメと共に約2時間半ほぼ休みなく展開しまして
その状況の一部を紹介するのみなりますが、
簡単にフィードバック!!
(後日、発表者が修正してくれるかも??)
ロシアのイメージのブレーンストーミング
でかい、寒い。
天然資源。
シベリア鉄道。
車が動かない。
結局、やっぱまとめられないので、
びっくりしたところをまとめました。
驚きロシア
・ロシア通貨ルーブル→日本円は、日本では交換できない!
(日本円→ロシアルーブルは、成田などで交換できるけど。。。)
・冬の日照時間は5時間。
(朝暗い時期に家を出て、学校帰るときも暗い)
・国際空港でも英語が通じない。
(町の中でも英語×、義務教育で英語は習うらしいが話せる人はほとんどいない)
・ベラルーシ、ロシア、リトアニアは自殺率が高い。
(10万人当たり30人以上、日本は25人ぐらい)
↑その原因の1つ。。
・アルコール中毒が多い。
(ウォッカが今年から値上げ)
・ロシア人は中国人が嫌い。
(日本人には優しい)
2010年05月07日
新歓発表「クジラとわたし」2010.04.30
「クジラとわたし」というテーマで、
捕鯨問題にからめて、
社会問題の捉え方を考える
コンセンサスを形成することの難しさを身にしみる
という目標で、社会学類の学生が発表してくれました。
調査捕鯨の今後について各々の立場になって話し合い
日本:商業捕鯨させて
漁師:生きる術を奪われたくない
消費者:クジラを食べたい
オーストラリア:海の生態系を守れ
SS:調査捕鯨、鯨は高等生物
日本では途上国などにIWCの加盟を促し、
議席数を増やして、IWCでの多数決で有利に立とうと画策している。
コンセンサスゲーム
http://d.hatena.ne.jp/elwoodblues/20071119/1195464816

;;;;;;;;;;;;;;;
6月6日(日)UNSAJ 春セミナー
平和構築についてのパネルディスカッション
早稲田大学、中央大学、創価大学
参加費1000円
<詳細はおって。。。。>
;;;;;;;;;;;;;;;
捕鯨問題にからめて、
社会問題の捉え方を考える
コンセンサスを形成することの難しさを身にしみる
という目標で、社会学類の学生が発表してくれました。
調査捕鯨の今後について各々の立場になって話し合い
日本:商業捕鯨させて
漁師:生きる術を奪われたくない
消費者:クジラを食べたい
オーストラリア:海の生態系を守れ
SS:調査捕鯨、鯨は高等生物
日本では途上国などにIWCの加盟を促し、
議席数を増やして、IWCでの多数決で有利に立とうと画策している。
コンセンサスゲーム
http://d.hatena.ne.jp/elwoodblues/20071119/1195464816
;;;;;;;;;;;;;;;
6月6日(日)UNSAJ 春セミナー
平和構築についてのパネルディスカッション
早稲田大学、中央大学、創価大学
参加費1000円
<詳細はおって。。。。>
;;;;;;;;;;;;;;;
2010年01月19日
日本の難民増加中!【1/19 活動報告】
日本にも難民がいる
って知ってますか??
2008年1599人が難民申請
するも、57人しか認定されず。
難民条約によると、
(1951年国連で採択、
1981年に日本は加盟し、難民認定制度を設ける)
難民とは・・・
人種・宗教・国籍、政治的意見または特定の社会的集団に属するなどの理由で、
自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた人々。
<難民鎖国 日本>
日本はその他の先進国に比べて難民受け入れ数が少ない。
アメリカ17000人、フランス・イタリア・イギリスなど10000人前後の受け入れあり。
日本はなんと50人前後。
申請者数で多いのは、
ビルマ(軍事政権下)、トルコ(クルド人)、パキスタン、イランなどなど。。
が、たとえば、
認定者数はトルコはゼロ。
∵クルド人を受け入れてしまうと、トルコ政府との関係が悪くなるためといわれている。
など、申請者数は年間1500人程度あるが、認定数は50名ほど。。。
なぜ難民は日本を選ぶか??
・安全に暮らせそう。手厚い保護を受けられそう。
・他国への逃亡のための経由地、日本でつかまった。
<日本の難民認定手続き>
難民認定申請
↓
法務省認定管理局が審査
(調査・インタビュー)
↓ ↓
認定 不認定
世紀滞在ビザ 収容・強制送還
法務省に入国管理局が設けられているほか,
地方入国管理局(8局),同支局(6局),
出張所(62か所)及び入国管理センター(3か所)が設けられています。
<収容所での暮らし>
自由に外へ出られない。
食事・シャワー・運動の時間が決められている・労働できない。。
職員による暴力行為・わいせつ行為・投薬ミス。
<牛久収容所>

定員700名の収容施設、常時500名程度の外国人が収容されている。
現在、157名の難民申請者がいる。
スリランカ33名、イラン21名、ビルマ18名、パキスタン13名、
バングラデッシュ13名、ネパール7名、ナイジェリア7名、トルコ6名などなど。
<強制送還は自己負担>
日本に借金して帰ることもできるが、
自国に帰っても、また迫害、住むところがない、働けない。
<CLOVER Care&LOVE for Refugee>
CLOVER ~難民と共に歩むユース団体~
知る、伝える、繋がる、行動する
という4つの活動を軸に活動している。
詳しくは
↓
CLOVERのブログ
http://cloveryouth.blog109.fc2.com/
日本はなぜ難民を受け入れないのか?
・メディアで移民が事件を起こすイメージが流れている。
・日本人は単一民族国家
・日本が受け入れるメリットは??
<感想>
・日本に難民がいるのを大学に来るまで知らなかった。
もっと多くの人が存在していることを知った上で話し合う必要がある。
・難民の人にも最低限の権利は与えるべき。
・問題が山積する日本の中で、優先順位を考えるべき。
・日本が難民を受け入れる、必要性・メリットを考えないといけない。
・今度、収容所に面会に行くときは連絡して欲しい。
・発表がわかりやすかったです。
:特別版PR:
1月20日(水) 18:00~18:30
ケンガクラヂオ 84.2MHz
ネットで聴けます!
http://www.simulradio.jp/
リンク先の地図の上にある、
ラヂオつくばをクリックしてください!
って知ってますか??
2008年1599人が難民申請
するも、57人しか認定されず。
難民条約によると、
(1951年国連で採択、
1981年に日本は加盟し、難民認定制度を設ける)
難民とは・・・
人種・宗教・国籍、政治的意見または特定の社会的集団に属するなどの理由で、
自国にいると迫害を受けるか、あるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた人々。
<難民鎖国 日本>
日本はその他の先進国に比べて難民受け入れ数が少ない。
アメリカ17000人、フランス・イタリア・イギリスなど10000人前後の受け入れあり。
日本はなんと50人前後。
申請者数で多いのは、
ビルマ(軍事政権下)、トルコ(クルド人)、パキスタン、イランなどなど。。
が、たとえば、
認定者数はトルコはゼロ。
∵クルド人を受け入れてしまうと、トルコ政府との関係が悪くなるためといわれている。
など、申請者数は年間1500人程度あるが、認定数は50名ほど。。。
なぜ難民は日本を選ぶか??
・安全に暮らせそう。手厚い保護を受けられそう。
・他国への逃亡のための経由地、日本でつかまった。
<日本の難民認定手続き>
難民認定申請
↓
法務省認定管理局が審査
(調査・インタビュー)
↓ ↓
認定 不認定
世紀滞在ビザ 収容・強制送還
法務省に入国管理局が設けられているほか,
地方入国管理局(8局),同支局(6局),
出張所(62か所)及び入国管理センター(3か所)が設けられています。
<収容所での暮らし>
自由に外へ出られない。
食事・シャワー・運動の時間が決められている・労働できない。。
職員による暴力行為・わいせつ行為・投薬ミス。
<牛久収容所>

定員700名の収容施設、常時500名程度の外国人が収容されている。
現在、157名の難民申請者がいる。
スリランカ33名、イラン21名、ビルマ18名、パキスタン13名、
バングラデッシュ13名、ネパール7名、ナイジェリア7名、トルコ6名などなど。
<強制送還は自己負担>
日本に借金して帰ることもできるが、
自国に帰っても、また迫害、住むところがない、働けない。
<CLOVER Care&LOVE for Refugee>
CLOVER ~難民と共に歩むユース団体~
知る、伝える、繋がる、行動する
という4つの活動を軸に活動している。
詳しくは
↓
CLOVERのブログ
http://cloveryouth.blog109.fc2.com/
日本はなぜ難民を受け入れないのか?
・メディアで移民が事件を起こすイメージが流れている。
・日本人は単一民族国家
・日本が受け入れるメリットは??
<感想>
・日本に難民がいるのを大学に来るまで知らなかった。
もっと多くの人が存在していることを知った上で話し合う必要がある。
・難民の人にも最低限の権利は与えるべき。
・問題が山積する日本の中で、優先順位を考えるべき。
・日本が難民を受け入れる、必要性・メリットを考えないといけない。
・今度、収容所に面会に行くときは連絡して欲しい。
・発表がわかりやすかったです。
:特別版PR:
1月20日(水) 18:00~18:30
ケンガクラヂオ 84.2MHz
ネットで聴けます!
http://www.simulradio.jp/
リンク先の地図の上にある、
ラヂオつくばをクリックしてください!
2010年01月14日
アホでマヌケな大統領選【1/12 定例活動について】
1月12日の学習会の準備をした忽那から報告させて頂きます。
新年明けましてということで、はじまった今回の活動ですが、
一発目は
「マイケル・ムーア in アホでマヌケな大統領選」を鑑賞し、

その感想と疑問点とを、1人1人自分の言葉で話してもらい、
お互いの理解を深めた後、
「表現の自由」について話し合いました。
アメリカでは表現の自由が守られているか?
日本ではどうか?
個人的には、原発しかり天皇制しかり、
少なくとも日本の大手のマスメディアには表現の自由はなく、スポンサー(広告主)の不利益になることは放送できない状況にあると考えています。
個人的に大好きな、清志郎さんの原発反対の歌とか、君が代のパンクロック版なども、発売禁止になった過去があります。
Cf.
9.11の直後に、ジョンレノンのイマジンが放送禁止になったという話をしましたが、
正確には「放送自粛」だそうで、他にも何曲か大手メディアで放送自粛になった曲があるそうです。
http://nvc.halsnet.com/jhattori/green-net/911terror/nyterror.htm#Music
このへんのリソースは確認できなかったので、真実は不確実ではありますが。。。
(ちなみに、9.11の犯人は未だに見つかっていないので、時間が許す方は上記URLより学んでみてください)
ウェブも全て監視されているっていうし、世の中有事の際にはどうなることか…。
恐いもんですね。
第3代大統領 トーマス・ジェファーソンの言葉
"Information is the currency of democracy."
情報は民主主義の通貨である。
Cf.
最近はこういう名言もあるらしい。。
"If information is the currency of democracy, then libraries are the banks."
もし、情報が民主主義の通貨ならば、図書館は銀行である。
アメリカの上院議員ウェンデル・フォード氏が1998年の図書館年次大会で行ったスピーチの言葉だそうです。
リソース:http://ifla.queenslibrary.org/faife/litter/subject/library.htm
さて、ということで、情報が思うように出せないと、民主主義は崩壊し、
有事の際に、戦争反対を叫ぶと捕まるあの時代に戻ってしまうのですね。
今の日本では、、、
危険な気がします。
そして、
2010年5月国民投票法( 日本国憲法の改正手続に関する法律)施行
7月参議院議員選挙
日本の行く末がどうなるか。2010年は重要な1年になるでしょう。
普天間基地の移転問題も、メディアに踊らされることなく、
1人1人が自分の意見を熟成させる必要があることは間違いないでしょうね。
そのためには世代を超えて、お話しする場所が必要です。
ってことで、
変えなきゃつくば
みなさんいかがでしょうか?
1月29日(金)19:00~
「参議院ってなんだろう?」
http://change.tsukuba.ch/
以上、宣伝を兼ねた報告でした。
続きを読む
新年明けましてということで、はじまった今回の活動ですが、
一発目は
「マイケル・ムーア in アホでマヌケな大統領選」を鑑賞し、
その感想と疑問点とを、1人1人自分の言葉で話してもらい、
お互いの理解を深めた後、
「表現の自由」について話し合いました。
アメリカでは表現の自由が守られているか?
日本ではどうか?
個人的には、原発しかり天皇制しかり、
少なくとも日本の大手のマスメディアには表現の自由はなく、スポンサー(広告主)の不利益になることは放送できない状況にあると考えています。
個人的に大好きな、清志郎さんの原発反対の歌とか、君が代のパンクロック版なども、発売禁止になった過去があります。
Cf.
9.11の直後に、ジョンレノンのイマジンが放送禁止になったという話をしましたが、
正確には「放送自粛」だそうで、他にも何曲か大手メディアで放送自粛になった曲があるそうです。
http://nvc.halsnet.com/jhattori/green-net/911terror/nyterror.htm#Music
このへんのリソースは確認できなかったので、真実は不確実ではありますが。。。
(ちなみに、9.11の犯人は未だに見つかっていないので、時間が許す方は上記URLより学んでみてください)
ウェブも全て監視されているっていうし、世の中有事の際にはどうなることか…。
恐いもんですね。
第3代大統領 トーマス・ジェファーソンの言葉
"Information is the currency of democracy."
情報は民主主義の通貨である。
Cf.
最近はこういう名言もあるらしい。。
"If information is the currency of democracy, then libraries are the banks."
もし、情報が民主主義の通貨ならば、図書館は銀行である。
アメリカの上院議員ウェンデル・フォード氏が1998年の図書館年次大会で行ったスピーチの言葉だそうです。
リソース:http://ifla.queenslibrary.org/faife/litter/subject/library.htm
さて、ということで、情報が思うように出せないと、民主主義は崩壊し、
有事の際に、戦争反対を叫ぶと捕まるあの時代に戻ってしまうのですね。
今の日本では、、、
危険な気がします。
そして、
2010年5月国民投票法( 日本国憲法の改正手続に関する法律)施行
7月参議院議員選挙
日本の行く末がどうなるか。2010年は重要な1年になるでしょう。
普天間基地の移転問題も、メディアに踊らされることなく、
1人1人が自分の意見を熟成させる必要があることは間違いないでしょうね。
そのためには世代を超えて、お話しする場所が必要です。
ってことで、
変えなきゃつくば
みなさんいかがでしょうか?
1月29日(金)19:00~
「参議院ってなんだろう?」
http://change.tsukuba.ch/
以上、宣伝を兼ねた報告でした。
続きを読む
2009年10月28日
初等教育の普及【10/27 定例活動について】
MDGs(ミレニアム開発目標)
Goal2:普遍的初等教育の達成-2015年までに世界中のすべての子どもが男女の区別なく初等教育の全過程を修了できるようにする。
Goal3:ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上-2005年までに初等・中等教育における男女格差の解消を達成し、2015年までにすべての教育レベルにおける男女格差を解消する。
どうやら達成できそうにない。
*初等教育・・・基礎的な知識・技能・態度を養うためのもの。「読み・書き・計算」
教育を受けられないと悪循環(親が貧しい→子どもが教育を受けられない→孫も…)
教育が受けられない人々がいる原因は…?
途上国では教師の数が少ないし(女性教師も少ない)、給料が安くて、あまり熱心ではない。
授業料は無料でも、教科書や制服が有料で通えない人もいる。(国際規約で授業料は無料にするようにというきまりになっている)
教育予算の配分が少ない(ex.インドは教育予算は全体の1%)
紛争など政情不安で通えない。物理的に遠い。教育の重要性を知らない。
言語の相違(教育される言語と日常言語の違いなど)
過酷な児童労働。(今生きることが優先される)
児童労働で社会が得られる利益<初等教育の普及で社会が得られる利益
という研究結果も出ている。
2つの就学率
総就学率・・・公式の就学年齢に相当する子どもの数に対する実際にその教育段階に就学している子どもの割合。
純就学率・・・公式に定めている就学年齢に相当する子どものうち実際に就学している子どもの割合。
で、2008年ユニセフの就学率調査データを見て・・・
データは地域全体の平均値
「最後の5%」
性別、民族、宗教的問題で通えない人を考えると、まだまだ教育100%は遠い目標。
ミレニアム開発目標の達成には、現在の3倍の資金援助が必要。
世界は今、何ができるか?
先進国
途上国の実情を聞く(支援費が無駄にならないように)
人の派遣
教育の必要性を説明
効率のよい教育ツールの開発
教育支援に対する理解
NGOの活用、ノンフォーマル教育
インフラ整備
途上国
支援の意思表示
自文化の再認識
→支援を受ける見返りの創出
国内格差是正
自国地域内人材活用
政情安定
教育支出を増やす
政策
教育必要性訴える
?? 疑問1 ??
教育をする=現行の西洋的な考え方の普及
ということは、絶対するべきことではないのではないでしょうか?
なぜ教育を勧めるか?
N.
・福祉国家的な自由の手助け、選択枝を広げる
→手助けは押し付けがましい
自由って何なのか?
T.
資本主義の概念が広がっている世の中において、外との接触を考えたらある程度の教育は必要
O.
生きていくために必要なものが教育であり、各地域に存在しているもの。
グローバリゼーションの波の中で、アメリカ的な考えの普及という部分がある。
H.
資本主義の世界の中で、国をなしていくためには資本主義的な考えは必要。
ブータンのGHPのような考えも面白いけど。
K.
大量消費社会を形成し、資本家に有利な状態を作るための戦略。
?? 疑問2 ??
途上国の支援をすることは必要か?
N.
国は国益を求めて行動する。人の才能は社会に還元すべきであり、国レベルでも同じで国の才能は世界に還元すべきである。
国は国益のために行動するべきだから
無償で提供すると調子に乗る。フリーライダーがある。
先進国の国民の税金が、自分たちのために使われない。
ので、善意での支援はいらない。
H.
植民地から資源を奪ってできた今の関係。
T.
強いものが弱いものを援助するものは当たり前だと思う。自分たちのお金を良いことに使えているいう気持ちになる。
K.
伝統・文化を大事にすべき。伝統文化を壊すような援助は必要ない。
O.
援助する時は、国益を考えてするべき。力がある国がその考えを広めているのは当然。
N.
スタート地点が違うから結果の平等を求める。
K.
お金で換算されない部分も多くあるので、国民的な感情なども関わってくる。
プレゼンについて
・発表に自信を持ってやるといいと思います。
・自分の意見をビシッと主張していいと思う。
・参考文献の掲示
・プレゼンの目的は何なのか?議論、意見交換、アイデア出し
・タイムマネジメント
感想
・根本を疑うっていうことが普段やっていないことで貴重な経験でした。
・「比較政治制度論」2008年9月
変数を用いてわかりやすいです(By Nさん)
次回は、
11月10日(火)18:30~
場所はのちほど。
テーマものちほど。
Goal2:普遍的初等教育の達成-2015年までに世界中のすべての子どもが男女の区別なく初等教育の全過程を修了できるようにする。
Goal3:ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上-2005年までに初等・中等教育における男女格差の解消を達成し、2015年までにすべての教育レベルにおける男女格差を解消する。
どうやら達成できそうにない。
*初等教育・・・基礎的な知識・技能・態度を養うためのもの。「読み・書き・計算」
教育を受けられないと悪循環(親が貧しい→子どもが教育を受けられない→孫も…)
教育が受けられない人々がいる原因は…?
途上国では教師の数が少ないし(女性教師も少ない)、給料が安くて、あまり熱心ではない。
授業料は無料でも、教科書や制服が有料で通えない人もいる。(国際規約で授業料は無料にするようにというきまりになっている)
教育予算の配分が少ない(ex.インドは教育予算は全体の1%)
紛争など政情不安で通えない。物理的に遠い。教育の重要性を知らない。
言語の相違(教育される言語と日常言語の違いなど)
過酷な児童労働。(今生きることが優先される)
児童労働で社会が得られる利益<初等教育の普及で社会が得られる利益
という研究結果も出ている。
2つの就学率
総就学率・・・公式の就学年齢に相当する子どもの数に対する実際にその教育段階に就学している子どもの割合。
純就学率・・・公式に定めている就学年齢に相当する子どものうち実際に就学している子どもの割合。
で、2008年ユニセフの就学率調査データを見て・・・
データは地域全体の平均値
「最後の5%」
性別、民族、宗教的問題で通えない人を考えると、まだまだ教育100%は遠い目標。
ミレニアム開発目標の達成には、現在の3倍の資金援助が必要。
世界は今、何ができるか?
先進国
途上国の実情を聞く(支援費が無駄にならないように)
人の派遣
教育の必要性を説明
効率のよい教育ツールの開発
教育支援に対する理解
NGOの活用、ノンフォーマル教育
インフラ整備
途上国
支援の意思表示
自文化の再認識
→支援を受ける見返りの創出
国内格差是正
自国地域内人材活用
政情安定
教育支出を増やす
政策
教育必要性訴える
?? 疑問1 ??
教育をする=現行の西洋的な考え方の普及
ということは、絶対するべきことではないのではないでしょうか?
なぜ教育を勧めるか?
N.
・福祉国家的な自由の手助け、選択枝を広げる
→手助けは押し付けがましい
自由って何なのか?
T.
資本主義の概念が広がっている世の中において、外との接触を考えたらある程度の教育は必要
O.
生きていくために必要なものが教育であり、各地域に存在しているもの。
グローバリゼーションの波の中で、アメリカ的な考えの普及という部分がある。
H.
資本主義の世界の中で、国をなしていくためには資本主義的な考えは必要。
ブータンのGHPのような考えも面白いけど。
K.
大量消費社会を形成し、資本家に有利な状態を作るための戦略。
?? 疑問2 ??
途上国の支援をすることは必要か?
N.
国は国益を求めて行動する。人の才能は社会に還元すべきであり、国レベルでも同じで国の才能は世界に還元すべきである。
国は国益のために行動するべきだから
無償で提供すると調子に乗る。フリーライダーがある。
先進国の国民の税金が、自分たちのために使われない。
ので、善意での支援はいらない。
H.
植民地から資源を奪ってできた今の関係。
T.
強いものが弱いものを援助するものは当たり前だと思う。自分たちのお金を良いことに使えているいう気持ちになる。
K.
伝統・文化を大事にすべき。伝統文化を壊すような援助は必要ない。
O.
援助する時は、国益を考えてするべき。力がある国がその考えを広めているのは当然。
N.
スタート地点が違うから結果の平等を求める。
K.
お金で換算されない部分も多くあるので、国民的な感情なども関わってくる。
プレゼンについて
・発表に自信を持ってやるといいと思います。
・自分の意見をビシッと主張していいと思う。
・参考文献の掲示
・プレゼンの目的は何なのか?議論、意見交換、アイデア出し
・タイムマネジメント
感想
・根本を疑うっていうことが普段やっていないことで貴重な経験でした。
・「比較政治制度論」2008年9月
変数を用いてわかりやすいです(By Nさん)
次回は、
11月10日(火)18:30~
場所はのちほど。
テーマものちほど。
2009年10月02日
夏休みよ再び!?【9/29 定例活動について】
まずは、
医学6年生の
国際生物学オリンピックトークに始まり、
中国「皆既日食」残念一人旅、
皆既日食は素晴らしいので、この先どっかでチャンスがあればぜひ見てください。
日本人初の宇宙飛行士、つくば市在住の毛利衛さんが宇宙飛行士を目指すきっかけとなったのは、子供の時に皆既日食を見たからだそうです。
中国一人ソーラン節演舞@天安門広場
世界人民大団結万歳
UNSAJ夏セミナー
核兵器よさらば!
医学生ゼミナール
鎌田實さん「正しいことをやっていれば、制度は後からできてくる」
暉峻淑子さん「労働は人の基本的な欲求の1つ」
→生活保護をもらって生きてるだけの人はつらい思いをしているので、就労支援や労働環境の改善などが急務である。現在の日本の完全失業者数は361万人。失業率は約5%と20人に一人は働きたくても働けない状況。自殺者数も過去最大のペースであり、「働く」ってことの見直しも必要だと思われます。
などの話で盛り上がりまして、
続いて、新代表のアメリカのコロラド州の大学に語学留学に行った話で盛り上がりました。

語学留学先では、リビアの人が複数人いたり、思っていた以上にインターナショナルな環境だったらしく、
語学は伸びたかわかりませんが、世界は広がったみたいです。
そして、リビアトークに花が咲き、
恋愛は悪、
リビアは核兵器のお手伝いをしていた、
リビアとリベリアをよく間違えるとか、
リビアとアメリカの国交回復の話だとかいったことを話しました。
また、夏休みは選挙があったという事で、
社会学類の選挙活動のバイトもやったという学生が調べてきてくれた、
日本の選挙制度
「小選挙区比例代表並立制」「中選挙区制」などのメリット・デメリット
のプチ学習会も開催されました。
で、
最後に事務的な話をしまして、
今後のイイラの活動予定とか、体制作りとか
また、
ぼちぼち人権デー
12月19・20日
のテーマ&発表者決定をしないとね~って話をしましたとさ。
以上、9/29の報告でした。
文責 筑波大学 医学6年生

医学6年生の
国際生物学オリンピックトークに始まり、
中国「皆既日食」残念一人旅、
皆既日食は素晴らしいので、この先どっかでチャンスがあればぜひ見てください。
日本人初の宇宙飛行士、つくば市在住の毛利衛さんが宇宙飛行士を目指すきっかけとなったのは、子供の時に皆既日食を見たからだそうです。
中国一人ソーラン節演舞@天安門広場
世界人民大団結万歳
UNSAJ夏セミナー
核兵器よさらば!
医学生ゼミナール
鎌田實さん「正しいことをやっていれば、制度は後からできてくる」
暉峻淑子さん「労働は人の基本的な欲求の1つ」
→生活保護をもらって生きてるだけの人はつらい思いをしているので、就労支援や労働環境の改善などが急務である。現在の日本の完全失業者数は361万人。失業率は約5%と20人に一人は働きたくても働けない状況。自殺者数も過去最大のペースであり、「働く」ってことの見直しも必要だと思われます。
などの話で盛り上がりまして、
続いて、新代表のアメリカのコロラド州の大学に語学留学に行った話で盛り上がりました。
語学留学先では、リビアの人が複数人いたり、思っていた以上にインターナショナルな環境だったらしく、
語学は伸びたかわかりませんが、世界は広がったみたいです。
そして、リビアトークに花が咲き、
恋愛は悪、
リビアは核兵器のお手伝いをしていた、
リビアとリベリアをよく間違えるとか、
リビアとアメリカの国交回復の話だとかいったことを話しました。
また、夏休みは選挙があったという事で、
社会学類の選挙活動のバイトもやったという学生が調べてきてくれた、
日本の選挙制度
「小選挙区比例代表並立制」「中選挙区制」などのメリット・デメリット
のプチ学習会も開催されました。
で、
最後に事務的な話をしまして、
今後のイイラの活動予定とか、体制作りとか
また、
ぼちぼち人権デー
12月19・20日
のテーマ&発表者決定をしないとね~って話をしましたとさ。
以上、9/29の報告でした。
文責 筑波大学 医学6年生
2009年09月02日
日米の安全保障 その1 報告
冷戦終了後から
安全保障は
国家の安全保障から、人間の安全保障へと変化していっている。
国連「脅威・挑戦及び変化に関するハイレベル委員会」報告書による
国家の安全と平和を左右する要素
1.国家間紛争
2.国内紛争(内戦、大規模な人権侵害、ジェノサイドなど)
3.貧困・感染症・環境悪化
4.大量破壊兵器
5.テロリズム
6.越境犯罪組織
(7.自然災害)
「欧州のための人間安全保障ドクトリン(欧州安全保障能力に関する研究グループによるバルセロナ報告書)」による
人間の安全保障が侵害される要素
・ジェノサイド
・拷問
・奴隷
・非人道的扱い
・失踪
・人道に関する罪
・戦争法の重大な違反
・食料、健康、住居
日米同盟で軍事的な安全保障は達成されているため、日本では人間の安全保障が充実してきた。

参加した1年生などの感想→ 2期生の新入生も参加してくれました!
2期生の新入生も参加してくれました!
「日米安全保障とか、軍事的なものとしか考えていなかったけど、人間の安全保障という新しい概念があるんだなと気付かされた。」
「今の状態では、まだ人間の安全保障を達成するのは厳しいかと思った。日本がイニシアチブをとっているのは知らなかったので、今後気に掛けてみたい」
「1学期にやったテスト勉強ではさらっとやったけど、今回は改めて考えられて良かった」
残りの時間で、
今後の日程などについて話し合い
*9月8日 →たかとし UNSAJの発表
9月15日→にっし UNSAJの発表
9月29日→よっちゃん 宇宙についての発表
10月以降は4年生などにも声をかけて、発表してもらう。
*発表のときに注意すべきこと
・静の分析
制度とか法律とかどう決まっているか?
・動の分析
実際の社会がどう動いているか?
主体の変化が出てきて、新しい方向性の研究が盛んになっている。
次回は、9月8日18:30~@1H201(予定)
いつもと場所・時間が違います!詳しくはまたのちほど
賢謙楽学と共催で大きくやります!
http://tsukuzemi.blog108.fc2.com/
安全保障は
国家の安全保障から、人間の安全保障へと変化していっている。
国連「脅威・挑戦及び変化に関するハイレベル委員会」報告書による
国家の安全と平和を左右する要素
1.国家間紛争
2.国内紛争(内戦、大規模な人権侵害、ジェノサイドなど)
3.貧困・感染症・環境悪化
4.大量破壊兵器
5.テロリズム
6.越境犯罪組織
(7.自然災害)
「欧州のための人間安全保障ドクトリン(欧州安全保障能力に関する研究グループによるバルセロナ報告書)」による
人間の安全保障が侵害される要素
・ジェノサイド
・拷問
・奴隷
・非人道的扱い
・失踪
・人道に関する罪
・戦争法の重大な違反
・食料、健康、住居
日米同盟で軍事的な安全保障は達成されているため、日本では人間の安全保障が充実してきた。

参加した1年生などの感想→
 2期生の新入生も参加してくれました!
2期生の新入生も参加してくれました!「日米安全保障とか、軍事的なものとしか考えていなかったけど、人間の安全保障という新しい概念があるんだなと気付かされた。」
「今の状態では、まだ人間の安全保障を達成するのは厳しいかと思った。日本がイニシアチブをとっているのは知らなかったので、今後気に掛けてみたい」
「1学期にやったテスト勉強ではさらっとやったけど、今回は改めて考えられて良かった」
残りの時間で、
今後の日程などについて話し合い
*9月8日 →たかとし UNSAJの発表
9月15日→にっし UNSAJの発表
9月29日→よっちゃん 宇宙についての発表
10月以降は4年生などにも声をかけて、発表してもらう。
*発表のときに注意すべきこと
・静の分析
制度とか法律とかどう決まっているか?
・動の分析
実際の社会がどう動いているか?
主体の変化が出てきて、新しい方向性の研究が盛んになっている。
次回は、9月8日18:30~@1H201(予定)
いつもと場所・時間が違います!詳しくはまたのちほど
賢謙楽学と共催で大きくやります!
http://tsukuzemi.blog108.fc2.com/
2009年06月23日
中国の民主化を考える
ついに1学期最後のイイラとなりました。即日更新に挑戦してみます!
今回は、「中国の民主化を考える」というテーマで、国際総合5年次4年の笹野万里恵さんが発表してくれました。
テスト前日にもかかわらず8名も参加してくれました。
【発表の概要】
1. Brain storming
・中国は社会主義国か?
・中国は民主主義国か?
党機関 行政機関 国家権力機関
中国共産党全国代表大会 国務院 総理:温家宝 国家主席:胡錦濤
中央委員会 総書記:胡錦濤 全人代
歴代国家主席
毛沢東(1949~1976)→鄧小平(1977~1993)→江沢民(1993~2003)→胡錦濤(2003~)
2.現代中国史概略
<計画経済の時代>
1945~1949年:国共内戦
1953~57年:第一次五カ年計画:“過渡期の総路線”の実施
1958年:第二次五ヵ年計画:“大躍進”運動の展開
1966~77年:“プロレタリア文化大革命”
<市場経済化・対外開放の時代>
Ⅰ.1978年5月 鄧小平政権掌握:改革・解放のスタート
「中国の特色を持つ社会主義」
経済改革
・ 階級闘争から現代化路線へ
・ 人民公社の廃止+生産請負制の導入
・ 企業経営請負制
・ 対外開放=外資導入
政治改革
4つの基本原則
① 社会主義の道
② プロレタリアート独裁
③ 共産党の指導
④ マルクス・レーニン主義と毛沢東思想
Ⅱ.1993~2003年 江沢民・朱鎔基体制
政策目標
・ 改革・発展・安定の関係のバランスをとる
・ マクロ・コントロール機能を強化し、金融財政面での適度な引き締めを維持する
・ 地方政治に過度に移譲された権限を中央に取り戻す
2002年2月 「3つの代表」思想
共産党は、①先進的な社会生産力の発展の要求、②中国の先進文化の前進の方向、③広範な人民の根本的利益、の3つを代表するという考え方
* 中国共産党の建前と中国社会の実像→格差の広がりが深刻
3.中国社会の変化
2003年(~2013年) 胡錦濤・温家宝体制
「親民路線」:格差対策、中産階層社会の誕生→政策の重点農村対策
世論の台頭
メディア改革とメディア規制:中国メディア=「党の喉と舌」
・ 党中央宣伝部による報道規制
⇔
・ 商業化されたメディア
・ ネット世論:中国のネットユーザー8000万人
・ 「政府情報公開条例」2008年5月施行
* 民意を政策にどう生かすかという議論
→経済と政治のずれ、改革のゆがみ
・・・中国は政治体制を変えなくても成長は維持できるか
4.民主化のシナリオ
>>呉軍華『静かなる革命 民主化へのグランド・ビジョン』
“2022年に中国は民主化する”
「大衆改革を契機とする体制移行」<「体制内の平和的変革」
・ 中国社会におけるコンセンサスの形成
・ 共産党内部の変革
・ 政治改革リーダー層の形成:教育的バックグラウンド+使命感
>>James Mann『危険な幻想』2007年
「気休めのシナリオ」:中国経済の発展が続けば、中国の政治改革に行き着く
「激動のシナリオ」:労働争議の頻発、農民運動→政治不安→劇的な政変、革命
「第三のシナリオ」:経済成長を続けるとしても、その政治体制は変わらない
・ 党は名称を変えるかもしれないが、政治体制の中核は普遍
・ 有力な反対政党も出ない。報道の自由、全国選挙もなし。
・ 中国の権威主義体制は今後も存続する。
はたして中国は民主化するのか?
・ 利得構造が変わらなければ難しい
・ 一人っ子政策で少子化が進むと改革はしにくくなるのでは?
・ 農民は減っている?→仕事がなく農村に戻ってくる人もいる
・ 民主化しないほうがうまくいくのでは?→格差がますます広がる
【おまけ】
先週の打ち上げで登場した料理たち
左から順にかよ、大滝、ノブ作です。
最後にデザートをみんなでおいしく召し上がりました
これで1学期のイイラもおしまいです。
2学期以降もこの調子でぶっちぎりで進んでいくためにも、みなさんブログへのコメントお願いします。