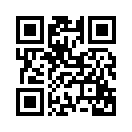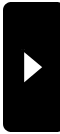2012年02月03日
突発的、豆まき(笑)
今日は通常通りの活動が終わったのち・・・ラーメン屋に行き・・・
きょうは
節分だ
ということに気付いた部員3名。
速攻カスミに行って豆を買い(奇跡的にまだ売ってたのね)
たっちんの家に直行。
おもむろに福豆を開けた部員。
皿に取り出す。歳の分つかむ・・・。もう10代も終わりなのか(寂)とおもわせる
豆よ、小さいのになぜおまえはそんなに雄弁なのか。
すると・・・
豆まきを始めた部員は、
地上戦に突入。
鬼はお前だとばかりに全力で豆をぶつけてくる部員。
こんなフォームは小学生のころのソフトボール大会以来だいと顔を紅潮させて命中させる部員。
ゆるい。
ゆるいぞ。
こんなのゆるい豆まきは初めてだ。
IIRAは豆まきもしてしまうのです。
そのあと部員は黙々と掃除。
豆は掃除しにくい。
豆が不思議に見えてくる。
そして落ち着いた部員は、そのまま2時間語り合って夜が更けてゆくのでした。
きょうは
節分だ
ということに気付いた部員3名。
速攻カスミに行って豆を買い(奇跡的にまだ売ってたのね)
たっちんの家に直行。
おもむろに福豆を開けた部員。
皿に取り出す。歳の分つかむ・・・。もう10代も終わりなのか(寂)とおもわせる
豆よ、小さいのになぜおまえはそんなに雄弁なのか。
すると・・・
豆まきを始めた部員は、
地上戦に突入。
鬼はお前だとばかりに全力で豆をぶつけてくる部員。
こんなフォームは小学生のころのソフトボール大会以来だいと顔を紅潮させて命中させる部員。
ゆるい。
ゆるいぞ。
こんなのゆるい豆まきは初めてだ。
IIRAは豆まきもしてしまうのです。
そのあと部員は黙々と掃除。
豆は掃除しにくい。
豆が不思議に見えてくる。
そして落ち着いた部員は、そのまま2時間語り合って夜が更けてゆくのでした。
2012年01月27日
今日はたっちんの発表!ところが・・・
今日は大石達也ことたっちん、
もとい
たっちんこと大石達也の発表の予定でありました。
しかしたっちん風邪によるダウンのため、今週は急遽新歓の話し合いとしました。
詳細は・・・教えられませんね^^
新入生の皆さん、こうご期待っ☆
ではっ
もとい
たっちんこと大石達也の発表の予定でありました。
しかしたっちん風邪によるダウンのため、今週は急遽新歓の話し合いとしました。
詳細は・・・教えられませんね^^
新入生の皆さん、こうご期待っ☆
ではっ
2012年01月20日
世界と日本の原発のこれから
今日は私、深澤左門が「世界と日本の原発のこれから」をテーマとしてプレゼントディスカッションを行いました。
東日本大震災に伴う東電福島第一原発事故が発生して間もなく1年が経とうとしています。
「フクシマ」という名を世界に知らしめたこの事故は、日本のみならず世界に大きな影響を与えています。
今日はまず現在の世界の原発の状況を俯瞰。
そこから原子力発電がどういう経緯で普及してきたのか、を解き明かし
今回の原発事故における政府対応の問題点、
そしてこれからの世界、日本で原子力発電はどういう方向をたどるのか
という流れで発表を行いました。
原発はこれからの日本・世界を語る上で不可欠のキーワードとなってきます。
これからの社会に生きていく私たちは、一人ひとりが原発に対してどういうスタンスを取るべきかを
きちっと決めていくべきだと思います。
世界の明日を担っていくのは紛れもない、私たちなのですから。
東日本大震災に伴う東電福島第一原発事故が発生して間もなく1年が経とうとしています。
「フクシマ」という名を世界に知らしめたこの事故は、日本のみならず世界に大きな影響を与えています。
今日はまず現在の世界の原発の状況を俯瞰。
そこから原子力発電がどういう経緯で普及してきたのか、を解き明かし
今回の原発事故における政府対応の問題点、
そしてこれからの世界、日本で原子力発電はどういう方向をたどるのか
という流れで発表を行いました。
原発はこれからの日本・世界を語る上で不可欠のキーワードとなってきます。
これからの社会に生きていく私たちは、一人ひとりが原発に対してどういうスタンスを取るべきかを
きちっと決めていくべきだと思います。
世界の明日を担っていくのは紛れもない、私たちなのですから。
2012年01月12日
日本の安全保障~中国の軍拡・海洋進出~
今日こそは真証君の発表を聞くことができました^^
いやぁ博識です
プロジェクターも使って戦闘機や地政学を講じながら発表を進めてくれました。
拡大を強める中国。私たちはどうすれば中国を正しく視ることができるのか、今日はそのヒントをくれたように思います。
とかく「軍事」ということに疎くなりがちな日本国民。私もその一人です。
しかし世界は軍事を前提に動いています。軍事への洞察は国際関係上非常に大切なのです。
僕ももっと勉強しなくちゃな!!
そんな気持ちにさせてくれた今日の発表でした。
いやぁ博識です
プロジェクターも使って戦闘機や地政学を講じながら発表を進めてくれました。
拡大を強める中国。私たちはどうすれば中国を正しく視ることができるのか、今日はそのヒントをくれたように思います。
とかく「軍事」ということに疎くなりがちな日本国民。私もその一人です。
しかし世界は軍事を前提に動いています。軍事への洞察は国際関係上非常に大切なのです。
僕ももっと勉強しなくちゃな!!
そんな気持ちにさせてくれた今日の発表でした。
2011年12月16日
たっちん初発表!「ニュージーランド」
今日は記念すべきたっちんの初発表でした。
テーマは「ニュージーランド」。
目の付け所が面白いですね。
NZの場所はわかる。でも、どういう政治で、どういう人々が住んでいる国なのか?
実はあまり知らない。
国際関係学上は一国一国への洞察は非常に重要です。
IIRAではこうした一国にピンスポットを当てた発表も行われます。
学問を概観・俯瞰する発表もあれば、スポットを当てて詳しくみる発表もあるのです。
あえて全然知らない国にスポットを当てて調べてみるということも面白いですね!!^^
それが自主ゼミの強み、面白さなんだなぁ。と思った今日この頃。
こうやってみんなで学びあっていこうね ^ω^
「学びあい」っていい言葉だな。それが学問の本当の姿なんじゃないだろうか。
そういう友を持てるっていいですね。
以上報告でした!
テーマは「ニュージーランド」。
目の付け所が面白いですね。
NZの場所はわかる。でも、どういう政治で、どういう人々が住んでいる国なのか?
実はあまり知らない。
国際関係学上は一国一国への洞察は非常に重要です。
IIRAではこうした一国にピンスポットを当てた発表も行われます。
学問を概観・俯瞰する発表もあれば、スポットを当てて詳しくみる発表もあるのです。
あえて全然知らない国にスポットを当てて調べてみるということも面白いですね!!^^
それが自主ゼミの強み、面白さなんだなぁ。と思った今日この頃。
こうやってみんなで学びあっていこうね ^ω^
「学びあい」っていい言葉だな。それが学問の本当の姿なんじゃないだろうか。
そういう友を持てるっていいですね。
以上報告でした!
2011年09月16日
9月16日の活動報告\(^o^)/
久方ぶりのブログ更新です。
毎度のことながら活動後すぐに更新すればいいものを先延ばしにしてしまい、すみません(・へ・)
9月16日は、『持続可能な開発とエコロジカル・フットプリント』というタイトルで国際2年 中川が発表させてもらいました。
内容は私が1学期に授業で習ったことをちょっとアレンジした感じです。
地球への環境負荷が問題になっている昨今、その負荷の度合いを客観的な数値として表わすのに様々なツールがあります。
そのうち2つを今回の発表で紹介しました。
その1-IPATの公式
どこぞのリンゴの会社の商品名みたいですが、違います。
I=P×A×T(Impact=Population×Affluence×Techonology)
の公式で環境への負荷を計ります。
簡単な練習問題を載せておきます、ぜひ考えてみてください(^^)
人口1000人の小さな2つの市を想像してください。A市とB市です。
A市はドーナツ化現象が進んでいるため、市民は全員、燃費の良い車(リッター15万km)を所有し、年間の平均走行距離は2万kmです。
一方、B市の状況は、ちょっと違います。公共交通機関が発達して、しっかりした都市計画に基づいて公共施設が整えられているため、車が必要な市民は半分しかいない。車の年間平均走行距離は、1万kmです。しかし、それらの車は旧式なので、A市の車よりも燃費が悪い。(リッター10万km)。
さて、この場合の燃料使用による環境影響を、IPATの公式を使って計算してみてください。
答えはコメントにて!!
その2-エコロジカル・フットプリント
エコロジカル・フットプリントとは、食糧や住宅、工業製品など人間が生きるために必要なものを生産したり、CO2など廃棄物を吸収・浄化するために必要な土地・水域面積のこと。
フットプリントをもとめる手順は以下の通りです。
①あるエリアの経済活動の規模を、土地や海洋の「表面積(ヘクタール)」に換算。
⇓
②その面積をエリア内人口で割って、1人あたりのエコロジカル・フットプリント(ha/人)を指標化。
⇓
③エリア適正規模(環境収容力)をどれくらい超えた経済活動をしているかが、一目でわかります。
この分析をするためのデータソースは国際機関から取ってくることが出来ます。
気になった方は、積極的に調べてみてください。
今回の発表では上の2つだけを紹介しましたが、まだまだあります。
IPATの公式もエコロジカル・フットプリントもそうなんですが、いろいろと考慮すべき点が抜けていて正確な環境への負荷を計ることが出来ているとは言えません。
でも、世界各国が自国の開発・発展のエゴを出し合う中で、環境負荷を客観的に計る指標が必要です。
そんなときに少しは役に立つと思いますよ。
以上報告でした。
ブログ更新めんどくさがりな性格を本当に反省しています。すみませんm(__)m
毎度のことながら活動後すぐに更新すればいいものを先延ばしにしてしまい、すみません(・へ・)
9月16日は、『持続可能な開発とエコロジカル・フットプリント』というタイトルで国際2年 中川が発表させてもらいました。
内容は私が1学期に授業で習ったことをちょっとアレンジした感じです。
地球への環境負荷が問題になっている昨今、その負荷の度合いを客観的な数値として表わすのに様々なツールがあります。
そのうち2つを今回の発表で紹介しました。
その1-IPATの公式
どこぞのリンゴの会社の商品名みたいですが、違います。
I=P×A×T(Impact=Population×Affluence×Techonology)
の公式で環境への負荷を計ります。
簡単な練習問題を載せておきます、ぜひ考えてみてください(^^)
人口1000人の小さな2つの市を想像してください。A市とB市です。
A市はドーナツ化現象が進んでいるため、市民は全員、燃費の良い車(リッター15万km)を所有し、年間の平均走行距離は2万kmです。
一方、B市の状況は、ちょっと違います。公共交通機関が発達して、しっかりした都市計画に基づいて公共施設が整えられているため、車が必要な市民は半分しかいない。車の年間平均走行距離は、1万kmです。しかし、それらの車は旧式なので、A市の車よりも燃費が悪い。(リッター10万km)。
さて、この場合の燃料使用による環境影響を、IPATの公式を使って計算してみてください。
答えはコメントにて!!
その2-エコロジカル・フットプリント
エコロジカル・フットプリントとは、食糧や住宅、工業製品など人間が生きるために必要なものを生産したり、CO2など廃棄物を吸収・浄化するために必要な土地・水域面積のこと。
フットプリントをもとめる手順は以下の通りです。
①あるエリアの経済活動の規模を、土地や海洋の「表面積(ヘクタール)」に換算。
⇓
②その面積をエリア内人口で割って、1人あたりのエコロジカル・フットプリント(ha/人)を指標化。
⇓
③エリア適正規模(環境収容力)をどれくらい超えた経済活動をしているかが、一目でわかります。
この分析をするためのデータソースは国際機関から取ってくることが出来ます。
気になった方は、積極的に調べてみてください。
今回の発表では上の2つだけを紹介しましたが、まだまだあります。
IPATの公式もエコロジカル・フットプリントもそうなんですが、いろいろと考慮すべき点が抜けていて正確な環境への負荷を計ることが出来ているとは言えません。
でも、世界各国が自国の開発・発展のエゴを出し合う中で、環境負荷を客観的に計る指標が必要です。
そんなときに少しは役に立つと思いますよ。
以上報告でした。
ブログ更新めんどくさがりな性格を本当に反省しています。すみませんm(__)m
2011年05月20日
5月21日 議事録
IIRA:議事録5月20日
Ⅰチベットの論点
1.チベットの人権をどう考えるか?
2.高度な自治とは?
3.歴史を見てどう思う?
4.宗教と国家
Ⅱ東トルキスタンの論点
1. チベットとの違い
2. 自治、独立へのアプローチ
3. 独立正当性(歴史を見てどう思う?)
Ⅲ中国の主張・国際社会の対応
1. 連邦制とは?
2. 国際社会の対応
3. 内政干渉?
4.なぜ延期のちの議論開始?
ICJは双方の同意が必要、安保理は勧告のみ
5.日本は中国の問題をどうとるか?
6.中国の民族問題との諸外国への影響
国際社会:国連、中国、モンゴル、インド、ロシア(ソ連)、アメリカ、イギリス、韓国、日本について
次回の集まり 5月27日(金) 9:40~ 3K2階ラウンジにて(予定)
Ⅰチベットの論点
1.チベットの人権をどう考えるか?
2.高度な自治とは?
3.歴史を見てどう思う?
4.宗教と国家
Ⅱ東トルキスタンの論点
1. チベットとの違い
2. 自治、独立へのアプローチ
3. 独立正当性(歴史を見てどう思う?)
Ⅲ中国の主張・国際社会の対応
1. 連邦制とは?
2. 国際社会の対応
3. 内政干渉?
4.なぜ延期のちの議論開始?
ICJは双方の同意が必要、安保理は勧告のみ
5.日本は中国の問題をどうとるか?
6.中国の民族問題との諸外国への影響
国際社会:国連、中国、モンゴル、インド、ロシア(ソ連)、アメリカ、イギリス、韓国、日本について
次回の集まり 5月27日(金) 9:40~ 3K2階ラウンジにて(予定)
タグ :UNSAJ
2011年02月10日
『地球温暖化の現状とこれから』 (2011/2/4)
連投です。ブログの更新が活動に追いつきました!
2011年2月4日は国際1年 井上愛さんに『地球温暖化の現状とこれから』というテーマで
発表していただきました。
参加者は堀江香世さん、井上愛さん、吉川ルノくん、原朋弘くん、中川雄貴です。
発表内容について報告しようかとも思ったんですが・・・
実は今 『IIRA×模擬国連筑波支部』 のコラボ企画を考えていて
今回の発表もそれに向けての下調べということだったんです。
ってことで内容の報告はこのイベント終了後に行います。
決してめんどくさいからとかそんな理由ではありません・・・
それでは盛大に イベント告知
イベント告知
『IIRA×模擬国連筑波支部』コラボ企画 テーマ『気候変動』
日時:2011年2月16日(水) 19時~
場所:教室3A311
IIRAや模擬国連に所属していない人でも興味のある方はぜひぜひ参加してください。
そして、その二日後の2月18日(金)はIIRA追いコンです。
楽しいことが続くイベント盛りだくさんのIIRAです。
2011年2月4日は国際1年 井上愛さんに『地球温暖化の現状とこれから』というテーマで
発表していただきました。
参加者は堀江香世さん、井上愛さん、吉川ルノくん、原朋弘くん、中川雄貴です。
発表内容について報告しようかとも思ったんですが・・・
実は今 『IIRA×模擬国連筑波支部』 のコラボ企画を考えていて
今回の発表もそれに向けての下調べということだったんです。
ってことで内容の報告はこのイベント終了後に行います。
決してめんどくさいからとかそんな理由ではありません・・・
それでは盛大に
 イベント告知
イベント告知
『IIRA×模擬国連筑波支部』コラボ企画 テーマ『気候変動』
日時:2011年2月16日(水) 19時~
場所:教室3A311
IIRAや模擬国連に所属していない人でも興味のある方はぜひぜひ参加してください。
そして、その二日後の2月18日(金)はIIRA追いコンです。
楽しいことが続くイベント盛りだくさんのIIRAです。

2011年02月10日
まとめて報告! (1/24、1/28)
今日も寒いですね、国際総合学類1年 中川雄貴です。
週に2回も活動してしまいました。もうすでに先月の話ですが・・・・・
1月24日(月)と1月28日(金)に、テーマはこれまでに引き続き「中国」です。
めんどくさがりなんでまとめて報告します。
すみません。
それでは1月24日の物理1年吉川ルノくんによる発表から報告します。
参加者は吉川ルノくん、井上愛さん、原朋弘くん、中川雄貴に加え
堀江香世先輩にも来ていただきました。
独立論文で忙しい中来てもらえてうれしいです。
発表内容は簡潔にまとめると
中国国内で民主化の気運が高まり、それが天安門事件という形に。
特に1989年におこった二回目の天安門事件が有名ですね。
その後に国家主席は江沢民から鄧小平になり
徹底した愛国教育の方針をとります。
この愛国教育により人民には中国(共産党政権)は正義、日本は悪という構造に!!
引き続き1月28日(金)国際1年原朋弘くんの発表についても。
今回の出席者は堀江香世さんに黒田さとみさん、原朋弘くん、中川雄貴
そして、国際1年の中国人留学生 たまちゃん にも来てもらいました。
ありがとう、たまちゃん
内容は
チベットとウイグル(東トルキスタン)それぞれと中国との関係について
歴史から詳しく調べてきてくれました。
調べてる中でも中立的意見、情報を見つけるのには苦労したみたいです。
そんな中で今回はたまちゃんが来てくれたということで
中国人留学生の視点からいろいろ意見を聞かせてもらいました。
①中国国内での少数民族について・・・
日常生活で民族について気にすることはほとんどなく
ましてや、学校などで友達に「何民族?」と聞くこともないとのことです。
日本人には民族という感覚にあまりなじみ無いですけど、日本でいう「部落」のようなものですかね。
また、少数民族に対して優遇措置もとられており
学校の試験などで少数民族の人のほうが合格点が低く設定されているということも。
中国国内を漢民族一色に染めようとするのではなく
afirmative actionで数ある民族の共生を実現させる政策なんですね。
②民主化について・・・
天安門事件のようなことはもう起こらないだろうかと疑問に思っていましてが
人口が人口なだけにたくさんある意見を総括するのに政党が一つしかないのは便利みたいです。
共産党の一党独裁に対して大きな不満が出てこない限りこのままの政治体制なんでしょうか。
今日、経済発展により豊かな層の人たちは政治の力を求めるようになるだろうし
貧しい人たちも生活していくための確かな生存権を確保するために政治に関心を持つのではないでしょうか。
活動報告に関しては簡潔にですが以上です。
今回のイイラのように実際に留学生と話すことができるのは嬉しいですね。
その国について深く知れるのはもちろん、外から見た日本がどのような感じなのかも知ることが出来ます。
筑波大学にはたくさん留学生がいるので積極的に誘っていこうと思います。
閲覧ありがとうございます。
週に2回も活動してしまいました。もうすでに先月の話ですが・・・・・
1月24日(月)と1月28日(金)に、テーマはこれまでに引き続き「中国」です。
めんどくさがりなんでまとめて報告します。
すみません。
それでは1月24日の物理1年吉川ルノくんによる発表から報告します。
参加者は吉川ルノくん、井上愛さん、原朋弘くん、中川雄貴に加え
堀江香世先輩にも来ていただきました。
独立論文で忙しい中来てもらえてうれしいです。
発表内容は簡潔にまとめると
中国国内で民主化の気運が高まり、それが天安門事件という形に。
特に1989年におこった二回目の天安門事件が有名ですね。
その後に国家主席は江沢民から鄧小平になり
徹底した愛国教育の方針をとります。
この愛国教育により人民には中国(共産党政権)は正義、日本は悪という構造に!!
引き続き1月28日(金)国際1年原朋弘くんの発表についても。
今回の出席者は堀江香世さんに黒田さとみさん、原朋弘くん、中川雄貴
そして、国際1年の中国人留学生 たまちゃん にも来てもらいました。
ありがとう、たまちゃん

内容は
チベットとウイグル(東トルキスタン)それぞれと中国との関係について
歴史から詳しく調べてきてくれました。
調べてる中でも中立的意見、情報を見つけるのには苦労したみたいです。
そんな中で今回はたまちゃんが来てくれたということで
中国人留学生の視点からいろいろ意見を聞かせてもらいました。
①中国国内での少数民族について・・・
日常生活で民族について気にすることはほとんどなく
ましてや、学校などで友達に「何民族?」と聞くこともないとのことです。
日本人には民族という感覚にあまりなじみ無いですけど、日本でいう「部落」のようなものですかね。
また、少数民族に対して優遇措置もとられており
学校の試験などで少数民族の人のほうが合格点が低く設定されているということも。
中国国内を漢民族一色に染めようとするのではなく
afirmative actionで数ある民族の共生を実現させる政策なんですね。
②民主化について・・・
天安門事件のようなことはもう起こらないだろうかと疑問に思っていましてが
人口が人口なだけにたくさんある意見を総括するのに政党が一つしかないのは便利みたいです。
共産党の一党独裁に対して大きな不満が出てこない限りこのままの政治体制なんでしょうか。
今日、経済発展により豊かな層の人たちは政治の力を求めるようになるだろうし
貧しい人たちも生活していくための確かな生存権を確保するために政治に関心を持つのではないでしょうか。
活動報告に関しては簡潔にですが以上です。
今回のイイラのように実際に留学生と話すことができるのは嬉しいですね。
その国について深く知れるのはもちろん、外から見た日本がどのような感じなのかも知ることが出来ます。
筑波大学にはたくさん留学生がいるので積極的に誘っていこうと思います。
閲覧ありがとうございます。
2011年01月16日
テーマ『インドの児童労働』 (2011/1/7)
 あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます
ブログの更新遅くなってすみません、国際総合学類1年の中川雄貴です。
2011年1月7日のイイラは国際総合学類の橋場奈月先輩に発表をお願いしました。
テーマは『インドの児童労働』です。
先輩が独立論文で研究していることを分かりやすく発表してもらいました。
まずは児童労働についての基礎知識を学び
そのあとに橋場先輩のインターンの経験なども交えながら
なぜインドで児童労働がなくならないのか
どうすれば児童労働がなくなるか
について考えました。
今回のイイラで一番気になったことは
先輩のインターンの経験談の中で児童労働をしている子どもに教育の大切さを教えても
すぐには分かってもらえなかったこと。
雇用者の前で下手なことは言えないとかいろいろ事情があるかもしれないけど
もしかしたら本当に勉強なんかしたくないのかも・・・
大人たちは自分が子どものときに働いていたから、子どもが働くのは当たり前。
その子どもたちは、もちろん働かなければ生きていけないという環境のせいだけれども
実際に勉強したことがなく、勉強することを知らないから
生きることに直接つながらない勉強をわざわざしようだなんて思わない。
「子供が働くことが当たり前」っていうその伝統・慣習が児童労働廃絶を邪魔しているんだなって。
一般の人々が教育の大切さについて知って、その悪しき慣習を終わらせなければいけませんね。
インドのNGOではそのような啓蒙活動も行われているようです。
でも、他にもたくさん問題が山積みで簡単には解決出来ない難しい問題です、児童労働問題。
次回は1月24日(月)に物理学類1年の吉川ルノくんが発表してくれます。